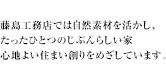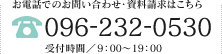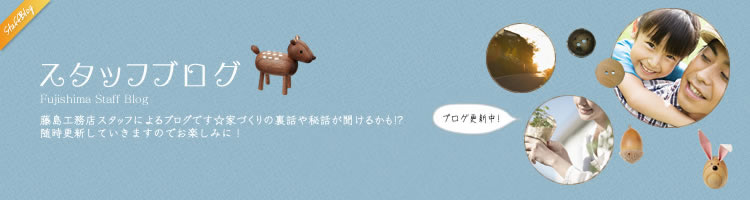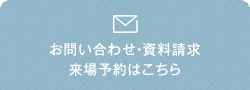1.サニーヒルズ南青山(隈研吾)

まず最初に紹介するサニーヒルズ南青山は南青山の住宅地の中に建つ地上3階のパイナップルケーキ店です。
設計は新国立競技場等の設計で注目を浴びている隈研吾氏によるもので、何といっても気になるのが一度見たら忘れられないその外観です。
「負ける建築」を標榜する隈研吾氏の建築は木や自然素材を使った建築が数多くありますが、ここまで派手な建築はこの頃の隈研吾氏の作品としては珍しかったです。
しかし作品のテーマは近年の隈建築で一貫していて、日本の木造建築に伝わる「地獄組み」という組み方を使いながら森のような、雲のような強くて柔らかい建築をつくりだしています。
2.アサヒビール吾妻橋ビル(フィリップ・スタルク+野沢誠)

隅田川沿いに見えるフィリップ・スタルクがデザインたアサヒスーパードライホールはいつ見てもインパクトが大きすぎる奇怪な建築です。
頂上のオブジェが何に見えるかは人それぞれですが、作者としては金色の炎をデザインしたもので、当初は縦にするつもりが構造や予算の関係などの紆余曲折を経て横になったとのことです。
この形については批判もあるようですが、今や隅田川沿いの風景のイメージを変え、多くの人が浅草の隅田川といえばこの建物を思い浮かべるようになったという点でこの形に価値はあるのだと思います。
最初に意図したものからはずれても、建築は公共性を持って長い年月そこに建ち続けます。
そして結果として人々に親しまれたり、時には批判されながら風景の一つになっていくのだと実感できます。
3.青山製図専門学校一号館(渡辺誠)


通称「ガンダムビル」と呼ばれるインテリア・建築系の専門学校です。
一見奇抜に見える建物の各パーツは単なる装飾ではなく、本来必要とされている機能から「成長」してこのような形になりました。
生物学の視点を取り入れ、機能を満たした上で進化や成長する建築は、後に同じ設計者に夜地下鉄飯田橋駅などでより具体的に実現することとなります。
4.ドーリック(隈研吾)


ドーリックはギリシャのドリス式の柱が巨大化しそのまま建築になったようなビルです。 側面は伝統的な3層構造で構成されており、近くに建つイオニア式の柱が巨大化した「M2」と対になる建築です。 設計者の隈研吾氏はこの時期、ポストモダンの理論を論じこのような建築を次々と発表していました。
バブルの崩壊と共にポストモダンの建築が終焉を迎えると、隈研吾氏は今までの理論がまるでなかったかのような環境に溶け込む建築・木の素材をふんだんに使った建築家に鮮やかに転身し現在に至ります。
現在では日本建築界の大家となった隈研吾氏のルーツを知るには欠かせない注目建築です。
5.モード学園コクーンタワー(丹下都市建築設計)


モード学園コクーンタワーは東京モード学園やHAL東京等が入る高さ204m、地上50階建て専門学校のタワー型校舎で、「創造する若者を包み込み、触発させる」という意味をからイメージされたコクーン(繭)のような外観が特徴で、建築そのものがメディアとなるようなインパクトがあります。
ちなみに外観の絹糸のような部材は構造体のように見えますが実は装飾だったりします。
ここまで紹介してきた不思議建築はすべてポストモダンの時代の建築で、それ故に過度な装飾やデザインが施されていましたが、バブル崩壊以降、派手で挑戦的な建築はあまり見られなくなっていた中、若者に向けたメディアとして久々の大規模プロジェクトがこちらのモード学園コクーンタワー。
*いかがだったでしょうか。
こうしてみるとやはりポストモダンの時代の建築が多くあるのが面白いですね。
東京にはまだまだ沢山の面白い建物があります。
引き続き、ご紹介していきますね☺